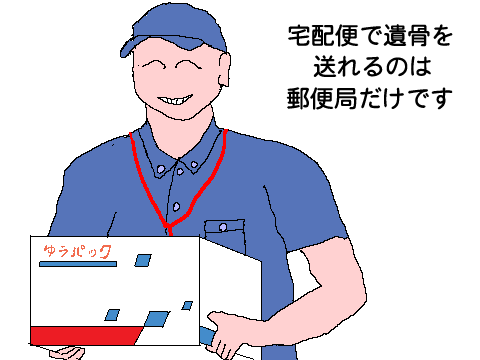骨壺の水抜きとは

墓じまいをする時には、お墓の中から遺骨を取り出す訳ですが、骨壺の中には必ず水が入っていますので、水抜きをする必要があります。
何故骨壺に水が溜まるのか

どうして水が溜まるのでしょうか…骨壺に水が溜まる理由に詳しく書いてありますが、お墓の納骨室(カロート)の中は暗くて湿度が高いために、骨壺の本体と蓋のわずかなすき間から湿度を含んだ空気が入ることで、朝晩の温度差によって結露した水滴が少しずつたまるのです。
お墓の蓋を開ける

お墓の中の骨壺を取り出すにはお墓の蓋を開ける必要があります。
危険な作業ですから二人以上で行うことが好ましい作業ですが、自分でお墓の蓋を開けることも可能ですので、誰にも頼めないような時には挑戦してみて下さい。
骨壺の蓋を開けてみる
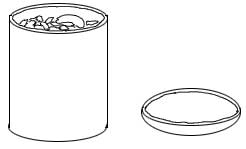
カロートから骨壺を出したら骨壺の蓋を開けて、中の様子を見て下さい、たまに骨壺の蓋が開かない時があって困ります…骨壺の蓋の開け方
骨壺に水が一杯にたまっている場合には、骨壺を持った瞬間に異常なほどの重たさを感じますので、開けたら本体のギリギリの所まで水がたまっていることがあります。
一杯に溜まっていなくても蓋を開けた時の蓋の裏に注目して下さい。
蓋の裏に水滴が付いていたり、湿っていたりすれば水が入っている証拠です。
骨壺の底に水抜きの穴が空いている骨壺では水が溜まることはありませんし、骨壺が古くて割れていたり、骨壺が倒れているような時にも水が溜まるようなことはありません。
また納骨したばかりの骨壺には水が溜まることはありません。
骨壺の水抜きの仕方

骨壺の中に水が溜まっているようでしたら、蓋を閉めてからすぐに空き地や排水溝がある所に持って行き、骨壺の蓋を押さえたままで横向きにしてみてください。
水抜きのコツ
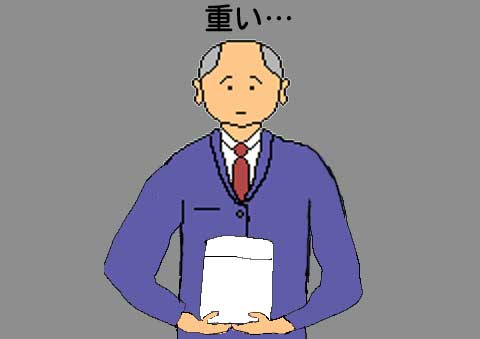
骨壺に溜まった水を抜く時のコツは、必ず蓋を押さえてから横向きにすることです。
そうしないと万一蓋が開いたら遺骨がバラバラと飛び出してしまいます。
蓋と胴体のすき間から水がチョロチョロと出てきます。水が出なくなるまで横向きにしておきます。
時間としては5分程度で水が止まるはずです。
骨壺の蓋を押さえる目的は、横向きにした時に蓋が取れて中の遺骨が飛び出さないようにするためです。
骨壺の蓋は大抵はねじ式か、ロック式になっていますが、たまに上に乗せてあるだけの蓋もあります。カロートから骨壺を取り出す時に異常に重たい時には、水が満タンに入っていると思って間違いありません。
水抜きをしますと中に入っていた水の重量が抜けますので、ずいぶんと軽く感じるはずです。
水抜きが済んだら

とりあえず大体の水が抜けたら骨壺の重さが軽くなっていることでしょう。
改葬して次のお墓に納骨するのでしたらそのまま持って行って納骨しても構いませんが、新しいお墓を建てたのでしたら、せっかくですから骨壺を新しくしても良いですし、そういう場合には遺骨を再火葬で乾燥させてから新しい骨壺に入れますと、とても気持ちの良いものです。
遺骨を取り出す時や墓じまいする時にお清め、お祓いが必要になりますが、必要でしたら私が高野山真言宗やすらか庵の僧侶をしていますので、お呼び下さればお伺いさせて頂きます。
自分で遺骨を乾燥するには

水抜きが済んだ骨壺の中の遺骨を自分で乾燥させるには、真夏の暑い日で猛暑日の朝から庭に新聞紙を広げて遺骨をまんべんなく広げ、夕方に取り込むことを一週間程度繰り返せば大体は乾燥します。
散骨などの目的で粉骨するために乾燥するのであれば、大きな骨の中に入り込んだ水分などは自然乾燥ではどうしても抜けきらないので、再火葬した方が良いと思います。
天日干しの方法は人に見られないような場所で行って下さい、見た方がびっくりしますから。