遺骨の重さはどれ位?
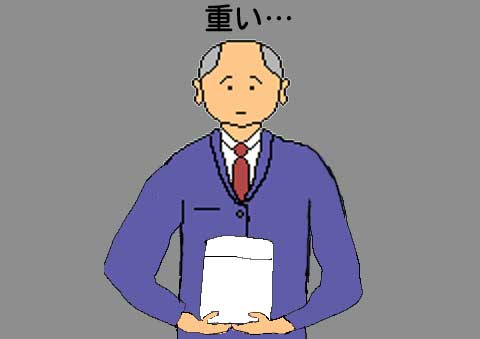
火葬後に残った焼骨(遺骨)の全ての重さは大人や子供、男女、年齢、病気の有無によっても変わりますが、一般的に大人の方の標準的な重量は2~3kgです。
関東と関西の収骨の違い

亡き人を荼毘に付して収骨するのに関東と関西では収骨する量が違っていて、関東では全部の骨を灰迄含めて収骨するのに対して、関西では一部の骨しか収骨しませんので、当然骨壺の大きさも違います。
関東では全量収骨

関東では火葬後に残った焼骨は全部骨壺に入れて持ち帰りますので、大人の方の遺骨で7寸(直径約21cm)の骨壺が標準で準備され、収骨時には遺族の人は故人の足の骨から腰、腹、胸、首、頭の順に収骨し、最後に一番上の真ん中に喉仏を乗せてその上に頭蓋骨を被せ、最後には火葬場の職員の人が箒と塵取りで残った灰まで集めて骨壺にいりますので、全量収骨とはまさにこのことです。
関東の大人の方の遺骨の重さは2~3kgで骨密度の高い人でしたら5kgを超えるようなこともあり、体格の良かった方なら8寸の骨壺(直径約24cm)を使用することがあります。
全量収骨する関東の場合で言いますと、遺骨の重さはそもそも大人か子供かで違ってきますし、男か女でも違いはあり、病気で闘病生活が長かった人は軽く、骨太の人は重くといった個人差があるのです。
知れば納得意外な事実…関東と関西では収骨の仕方が違う
関西では部分収骨

関西では火葬後の焼骨は、遺族の人が故人の足の骨から腰、腹、胸、首、頭の順に収骨しますが、準備された骨壺は5寸(直径15cm)の骨壺が標準サイズになりますので、全部の遺骨を納めることが出来ません。
足、腰、腹、胸、首、頭の主要な部位でしかも小さい骨ばかりを入れますので、火葬後の遺骨が乗っていた台には収骨後であってもほとんどの遺骨が残っていますが、参列した人はのことについて全く気にしていません。
火葬場の職員の人の説明によりますと、残った焼骨は決められた場所に供養の上で埋葬されるそうです。
関西では収骨された遺骨の重さは1~2kgといった感じになります。
骨が軽い人
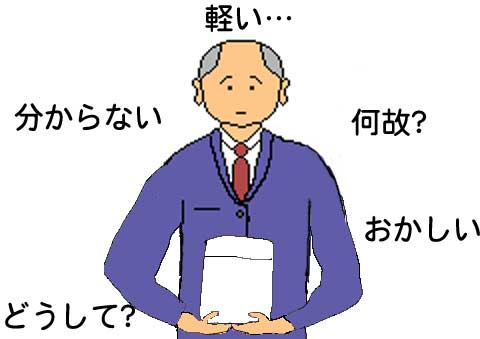
骨が軽い人とは病気や老衰などで骨の組織が脆くなった人のことで、自分の身体を支えることが出来ずに寝たきりになったわうな人が亡くなって火葬されますとボロボロになった骨が残ります。
闘病生活が長かった人
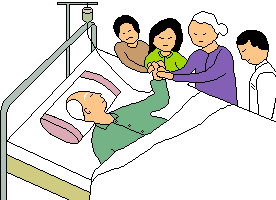
病院での闘病生活が長かった人で、少しずつ痩せていった人が亡くなった時には遺骨が意外と軽くなっていることがあり、薬などの影響を受けたことにもよりますが、体がやせるということは骨まで痩せるということでもあるのです。
ただし骨が痩せるということは相当に長い時間が掛かっている訳で、何年も寝たきりだった方の骨は、少しずつ弱くて脆くなっているのです。
病気などで苦しまれた方の遺骨を粉骨する時には労いの言葉を掛けながら粉骨して差し上げましょう、死に対する恐怖を人一倍経験されたのですから、供養の気持ちが必要です。
供養の粉骨は…粉骨供養
病気が長引いた方の遺骨は大量に投与された薬剤などの影響により、火葬したあとに色が付いていることもありますが、この色については、様々な要因があります。
遺骨の色がピンク、緑!?…遺骨に色が付いている理由
骨粗しょう症の人

骨粗しょう症の人は大変に遺骨が軽くて脆いのが特徴です。
骨がヘチマやスポンジみたいに空洞が多くなっていますので、見ればすぐに分かります。
特に背骨がボロボロになっていることが多く、骨粗しょう症が進行すれば自分で自分の身体が支えきれなくっなてしまいます。
骨粗しょう症の人の焼骨は指で押しても崩れるぐらいになっていることがありますので、粉骨する時にはすりこ木1本で出来ることがありますが、それでも手足の骨はある程度硬いものです。
骨が重い人
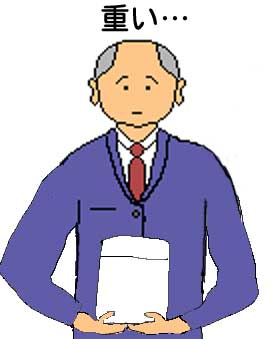
働き盛りの人が事故で亡くなった、最後まで元気で天寿を迎えたような人が亡くなって火葬されますと、硬くて重く、しっかりとした形のある遺骨が残ります。
事故で亡くなった若い人の骨は重い
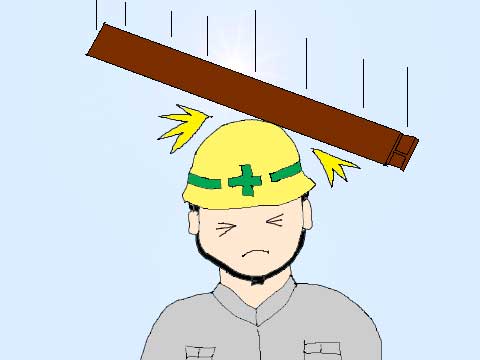
元気な若い人が事故で亡くなったような場合や、急に倒れて亡くなった場合には焼骨が大変に重いということがあります。
関東での大人の方の遺骨を入れる骨壺のサイズは普通7寸で直径約21cm程度ですが、たまにですが大柄の方で急死された方の遺骨は規格外の8寸で直径約24cmの骨壺に納められることがあります。
遺骨の重さの最大と最小は

大変に軽い人でしたら遺骨の重量は1kgぐらいしか無いこともありますし、重い人でしたら遺骨の重量はたまにですけれど5kgを超えるようなこともあります。
5kgはスーパーで売っているお米の1袋の重さですから、結構重たいと感じます。
骨太であった人の遺骨はとても重たく、職業では力士、プロレスラー、柔道家などの方が亡くなった時の遺骨は最高に重たく、私がこれまでに経験した中での最高の遺骨の重さは7kg程度でした。
粉骨しても重さは同じ

この遺骨の重量は粉骨しても変わることはありません、粉骨すれば大きさ(容量)は三分の一程度になりますが、重さ自体は変わりません。
但し骨壺に入った状態から粉骨して水溶性の袋に入れて持ってみますと、随分と軽くなったように思いますが、これは骨壺自体の重さが無くなったからです。
粉骨して入れ物に入れる

遺骨を粉骨して入れ物に入れるのなら最大で2リットル入る入れ物を準備すれば大抵は納まります。
屋外のお墓を墓じまいしてカロートから取り出した遺骨を粉骨するには再火葬か乾燥が必要になります。
粉骨して容器に入れるなら

関東での標準の骨壺に入った遺骨を粉骨して容器に入れるのなら2リットルの容器が必要です。遺骨の量が少ない方や関西では1リットルの容器で入ります。
遺骨の量がとても多い方で2リットルの容器に入らないことがたまにありますが、その場合には、容器に入れた遺骨(遺灰)をスプーンなどでぎゅうぎゅうと押さえつけてみて下さい、そうすればかなり沈みますので、まだ入れることが出来ます。
写真の左は7寸の骨壺で右は2リットルの容器です。
粉骨してチャック付袋に入れるのなら

遺骨を粉骨してチャック付きの袋に入れるのなら最大で200×280mmの袋が必要で、一般的には140×200mmの袋で間に合います。
粉骨して水溶性袋に入れる

粉骨する目的が散骨することですから、ほとんどの方が水溶性袋に入れることになります。
水溶性袋とは水に溶ける袋のことで、海の散骨の時に使いますが、散骨に参加する人数分に分ければ皆が散骨に参加することが出来ますし、遺骨(遺灰)を残さずに散骨することができるので便利です。
水溶性袋について詳しく…海の散骨に使う水溶性袋とは



コメント