お墓に遺骨を納骨とは
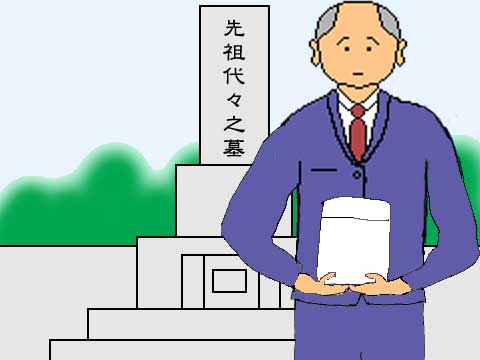
お墓の地下部分にはカロートと呼ばれる納骨室があって、その中に骨壺に入った遺骨を納めることを納骨と言い、一般的には四十九日の法要が済んでお墓に行って納骨します。
納骨する時期は
火葬が済んだ故人の遺骨はしばらくの間自宅に安置して、ある程度の日時が過ぎてから納骨することになります。
四十九日で納骨

亡くなった方の火葬が済んで遺骨を骨壺に入れて家に持ち帰り、四十九日の祭壇にお祀りして四十九日の期間が済めば満中陰の法事ということで僧侶や親族に集まってもらい、法事を済ませた後にお墓に行って遺骨を納骨します。
納骨すべきお墓が既にある場合には四十九日の法要の後で納骨という事が一般的に行われます。
一周忌で納骨
故人が亡くなってから一年経過した命日に行うのが一周忌の法事で、四十九日の時にお墓が準備出来なくて、一周忌を目途に墓地を購入して墓石が完成した場合には、一周忌の法事の後に納骨に向かいます。
新規の墓地の場合には納骨の時にお墓の開眼供養もしてもらいます。
一周忌は故人が亡くなって一年目の節目となり、悲しみの感情もやっと薄れた頃になり、それでもまだ葬儀からの延長という感覚がありますので、気持ち的にはスムーズに進みます。
三回忌で納骨
故人が亡くなって三回忌までは葬儀の延長というイメージがあり、一周忌の次の年ですから、三回忌までは葬儀の流れの連続として行われます。
お墓をなるべく早く準備しようと思っていても、実際に見に行ったり複数の霊園を比較検討したり、どのような墓地が故人にふさわしいかなどを決めるのに結構時間が掛かるものです。
新規の墓地の場合には納骨の時にお墓の開眼供養もしてもらいます。
三回忌の法事が済んでから納骨に向かいます。
その他の時期に納骨
自滝にお祀りしている遺骨は急いで納骨する必要はありません。
既にお墓のある人の場合には一般的には四十九日の法事が済んでから納骨に向かいますが、納骨べきお墓が無い場合には自宅にそのままお祀りし続けることになります。
しかしながら何時までも自宅に安置し続けますとやはりお墓に入れてあげないと可哀そうだと思うものです。
三回忌に間に合わなかったら5年目でも10年目でも構いませんが、七回忌とか十三回忌などの法事に合わせて納骨するのが通例で、故人の納骨が親族などにお披露目できるからなのです。
実際の納骨は
実際に納骨するには親族に連絡したり霊園の管理事務所や石材店に連絡したりの前準備が必要になります。
納骨の準備

公営霊園や民間霊園、納骨堂に遺骨を納骨する場合には、管理者に申請してください。自分達でお墓の蓋を開けて納骨することは、遺骨の管理上のトラブルになってしまいます。
霊園の管理者はお墓の中に誰の遺骨が納骨されたかを管理していますが、これは改葬時や墓じまい時に、改葬許可申請書に遺骨の証明をしてもらう必要があるからなのです。
納骨の際には納骨する遺骨が間違いなく故人のものであることを証明する「埋葬許可証」が必要になります。
埋葬許可証は火葬した際に発行されたもので、火葬場や葬儀社から手渡しされているか、骨壷の桐の箱に入っていることが多いです。
許可が降りれば管理者立会いの下納骨することになります。
お寺が管理する墓地に納骨する場合には石材店と僧侶を手配します。
四十九日などの法要と納骨時には僧侶には読経してもらい、石屋さんには納骨室の蓋石を開け閉めしてもらうための予約をしておきます。
この場合にも「埋葬許可証」の提示が必要となります
納骨式
納骨式の時には僧侶や神官の供養と石材店の立会いが必要となり、事前に手配しておきます。
霊園の管理事務所には予め連絡し納骨の手続きをしますが、納骨式当日でも手続き可能です。
亡き人の遺骨をお墓に入れることで亡き人の安住の場所になる訳ですから、以後にお墓参りに来る方のためにも、お披露目と言う意味で親族や友人などに来てもらいます。
四十九日の法要が済んでから遺骨を持ってそのまま納骨に向かうという流れが一般的です。
納骨式の流れとしては
- 僧侶読経
- 焼香
- 納骨
- 焼香
- 僧侶の法話
- 喪主挨拶
納骨式が済んだら参加者には精進落としの料理を振る舞います。
僧侶に対する御布施は四十九日の法要と共に御渡しします。

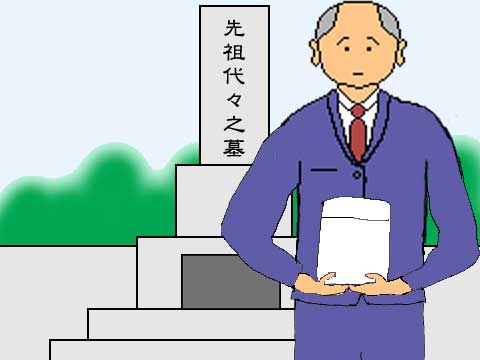
コメント