自然葬とは

自然葬とは亡き人の遺体や火葬後の焼骨を墓地に納骨することなく、海や山などの自然に還すことを目指した葬送の方法。
自然葬の由来
私達の祖先は狩猟採集の生活を送っていた縄文時代にはムラを作って集団生活をしてお互いに助け合い、死者が出ると村はずれの特定の場所に放置或いは埋葬していましたが、死者は動物に食い荒らされたり虫や微生物に分解されて自然に還っていきますので、古い時代の遺骨が現代まで残るようなことはほとんどありません。
有史以来の私達の祖先のほとんどが子孫を残して自らの生命を全うした後に分解されて自然に還り、次なる生命の糧となることを延々と繰り返してきたのですから、私達も地球上の生命の一員であることを思えば、死して何かを残すのではなく、何も残さずに自然に還ることが使命なのです。
自然葬の種類
死して自然に還る自然葬には大きく分けて遺体を火葬することなく自然に還す方法と、火葬した焼骨を粉砕して自然に還す方法の二通りがあります。
火葬しない自然葬

火葬しない葬送には土葬、鳥葬、風葬、水葬、があります。
土葬とは

土葬とは死者の遺体をそのまま、或いは棺桶に入れて穴を掘り、土の中に入れてから上に土を被せる方法で、本来の埋葬とはこの方法を言います。
我が国では火葬が普及していますのでほとんどの方が火葬になり、山間部や離島などで火葬の利用が困難な場合に限っての土葬が認められていますが、例外的な扱いであり、土葬を希望する人が自由に利用出来る訳ではありません。
我が国では昭和の初め頃まで一般的に行われていた葬送です。
鳥葬とは
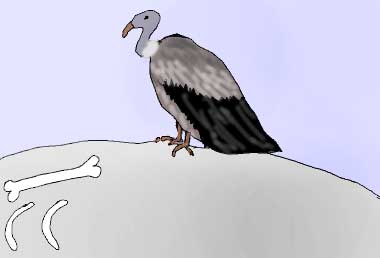
鳥に食べられるということは惨いことのように思われますが、人の身体は地球上の生命の一員として例外ではなく、最後は他の動物に食べられるということが当たり前のように行われてきました。
鳥葬とはチベットの高地で行われている葬送で、岩の上に切り刻んだ死者の肉体を置くことにより、鳥に食べさせるのですが、死者の魂が鳥と共に大空に羽ばたいていくことで天に上ると考えられています。
チベット高原のように標高の高い所では火葬するための薪は貴重品であり、大量に使うわけにはいきませんし、肉食の動物としてはハゲワシが生命連鎖の上位になり、実際の鳥葬の時には無数のハゲワシが肉を取り合います。
風葬とは
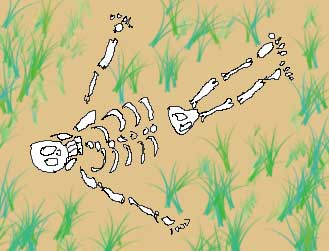
風葬とは死者の遺体を自然の中に放置することで、動物に食べられたり昆虫などに分解されて自然に還っていきます。
我が国の縄文時代や弥生時代には人が死ぬと野原に放る(ほふる)ことが葬る(ほうむる)の由来であったように、死ぬということが他の動物の死と同じことであり、一般庶民が墓を作るようになったのは江戸時代以降です。
風葬は野山に置き去る方法ですから葬儀のような儀式は行われません。
水葬とは

水葬とは死者の遺体を川や湖、海などに投げ入れることで、魚やサメなどに食べられたり水生生物に分解されて自然に還っていきます。
外洋を航行する船舶ですぐに港に寄ることが出来ない場合などに限って国際的に認められた葬送の方法でもあります。
焼骨の自然葬

現代では少子高齢化、人口の減少などが進行していくにつれ、後継者の居ない人が増え続け、お墓を維持できなくなっての墓じまいも増えています。
子々孫々まで続くお墓という価値観も崩れてしまい、後継者不要の樹木葬や散骨を利用する人が増えているのです。
骨壺に入れられた焼骨はお墓の中に納骨しても自然に還ることはありませんが、遺骨を粉骨して海や山に散布する散骨はやがて自然に還っていきますので、自然葬と言われています。
最近では自宅の庭に散骨する人も居ますが違法ではありません。
海の散骨

海には個人的な所有権がありませんし、誰でも自由に立ち入り出来ますので、散骨を利用する人のほとんどが海の散骨ということになります。
海の散骨では焼骨を粉砕したものを水溶性袋に入れて船で沖合に出て儀式を行い、お花などと共に海中に散布します。
山の散骨

山は個人や法人の所有か国有地でありますので、許可をとる必要がありますが、許可が得にくいという問題があります。
自分で所有する山でしたら粉骨した焼骨を散骨しても全く問題ありません。
自宅の庭に散骨

引越するようなことが無い事が確実な自宅の庭に散骨することは違法ではありません、合法です。
但し近所の人にやたらと言わないことで、それは散骨を快く思っていない人が居て、感情を害するかもしれないからです。
自宅の庭に散骨する時には出来るだけ上を歩かない場所で木の根元などが理想の場所です。


