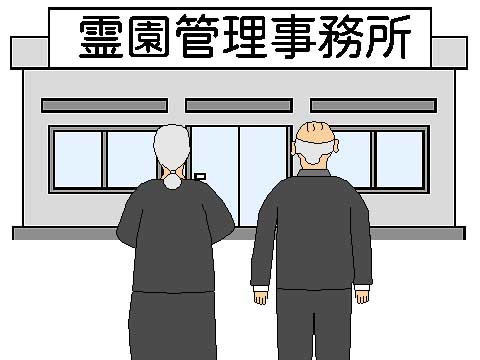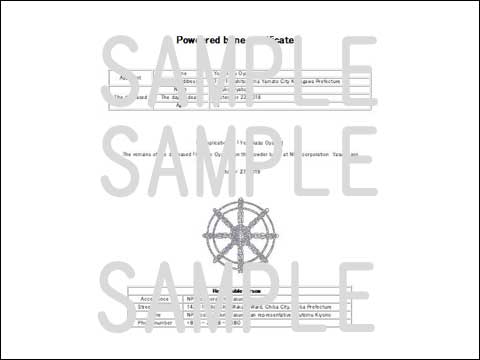拝石とは

拝石とは「おがみいし」「はいせき」とも言い、お墓を拝む時に人が上に乗る石のことで、関東ではお墓のカロートの蓋の役割もしています。
水を入れるための水鉢が乗っている板石は「水板」と言います。
拝石の役割

お墓は亡き人の遺骨を埋葬する場所ですが、もう一つの役目として黄泉の国の入り口でもあります。
死者の国の入り口が開いたままの状態では誰かが迷い込んでしまうことになってしまうので、そのようなことが無いように蓋をするのです。
古い時代の墓石は亡き人の遺体を埋葬した場所の上に自然石を上に載せるだけの単純なものが多かったのですが、自然石の役割は遺体が動物に掘り起こされて食い荒らされないように、なるべく重たい石を載せたのです。
古代には死者の魂は身体から抜け出して悪さをすると言い伝えられ、死者が悪さをしないようにと重たい石を載せたとも言われています。
お墓の蓋の石は御影石で作られていることが多く、ある程度の面積と厚みがありますので、結構な重量であり、場合によっては20~30kgと大人二人が持たないと持ちあがらない程の重さがあります。
拝石を開けるのに許可が必要ですか?
一般的に霊園内の墓地で拝石を開けるのは納骨式の時であり、納骨式では宗教者を呼んでお祓いをした後に石材店が拝石を開けて遺骨を納骨し、立ち会った親族などが焼香後に石材店が拝石を閉めます。
亡くなった人の遺骨を新たに墓地に納骨するには故人の火葬時に発行された「埋葬許可証」が必要であり、法律で定められた埋葬行為になりますので、事前に霊園の管理事務所に届け出が必要です。
自分で勝手に拝石を開けて無許可で納骨することは法律違反になります。
誰が拝石を開ける?
墓地の拝石を開ける理由として遺骨を納骨する場合には石材店に頼み、単に中を確認するだけでしたら自分で開けることも可能ですが、拝石は重量があって持ち上げたり動かしたりする作業はとても危険ですから、石材店に頼むことをおすすめいたします。
石材店に頼む
納骨式の時には事前に管理事務所に納骨の申請をし、宗教の司祭者を呼ぶこと、親族に連絡すること、そして石材店には墓誌に故人の名前を入れることと納骨式の立会いの予約をしておく必要があります。
石材店は事前に墓誌に故人の名前や没年月日などを彫り、納骨式当日にはパラソルや焼香台の準備と、拝石の開け閉め、遺骨の納骨をしてもらいます。
納骨式の時の拝石の開け閉めは納骨の立会いと言う意味合いがありますので、石材店に頼みましょう。
自分で開ける

お墓に新たに納骨する必要が出てきた時や、墓じまいする時に誰の遺骨が入っているのかを確認する時には、お墓の中を知っている人に聞いてみる方法が一番良いのですが、案外覚えていないもので、以前納骨する時に立ち会った人であっても年月の経過と共に記憶が曖昧になっているものです。
そういう時にはお墓の蓋を開けてみて確認するのが確実な方法で、間違いが起こらない方法です。
お墓の蓋はお墓の使用者或いは使用者が許可した者であれば誰が開けて構いません。
墓石の所有権は使用者にあるのですから、全くの合法です。
亡き人が眠っている石室の蓋を開けることは霊的な影響を受けそうで怖いという人は僧侶に拝んでもらって石材店に開けてもらいましょう。
自分で出来る人は、お墓の蓋をバールを使ってお墓の蓋を開けてみて下さい。
お墓の蓋の開け方に詳しく書いてあります。
お墓のカロートの中は実に暗くてジメジメした陰湿な環境ですから、時々は新鮮な空気と温かい日差しを入れて差し上げれば快適な空間になります。
ついでに骨壺も外に出してあげて日光浴させてあげましょう。