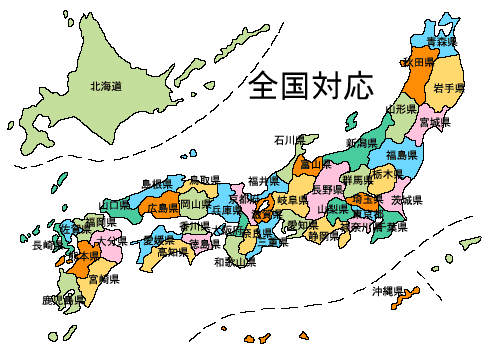水が溜まらない骨壺とは

水が溜まらない骨壺とは、お墓の中の湿気が原因で骨壺に水が溜まることを防ぐため底に小さな孔が開いた骨壺のこと。
お墓の中の骨壺に水が溜まる理由

墓じまいの時にカロートの中から骨壺を取り出しますと、ほとんどの場合骨壺の中に水が一杯に溜まっていて、まず最初にするべきことは骨壺の水抜きであり、蓋を押さえたまま横向きにしますと、水がチョロチョロとすき間から流れ出します。
くれぐれも中に遺骨をこぼさないように…骨壺の水抜きの仕方
水が流れ込んだ訳でもないのに…お墓の中の骨壺に水が溜まる理由
お墓の中の環境は一年中真っ暗で湿気が多く、隙間から入り込んだ水分が外に出にくいこともあって、高い湿度の空気が骨壺の隙間から入り込み、それが朝晩の温度差によって水滴となって溜まっていくのですが、一日一滴の水滴であっても長い年月溜まり続けたら、ついに骨壺一杯の水になるのです。
水が溜まらないアイデア

さて骨壺に水が溜まるという事は昔からの常識であったようで、亡き人の遺骨が水の中に溺れている光景はあまり好ましい光景ではないと思いますし、骨壺を作る陶器屋さんもそれに対する工夫をする人がいたもので、このように底に穴の開いた骨壺を時々見かけます。
骨壺の底の中央に丸くて小さい穴が開いただけのことで、他は一般的な骨壺と何も変わりません。
この骨壺のメリット

お墓の中に納骨された骨壺は一旦納骨したらもう開けて中を見るようなことは無いものです。
しかし長い年月の間に故人の遺骨が水浸しになっていますと、遺骨が苦しむようなことはありませんが、世の中不思議なことがあるもので、誰かが池で溺れるような夢を見ることがあるかもしれません。
後継者が居ないなどの理由で墓じまいする時に、お墓から取り出した遺骨の入った骨壺は必ず水抜きする必要がありますが、穴あきの骨壺は水抜きの必要がありません。
この骨壺のデメリット

これは完全にお墓に納骨することを前提とした骨壺でありますが、一つだけ欠点があり、それは遺骨の粉が底からこぼれるというものです。
今の時代皆がお墓の納骨するのではなく、散骨する人も居るのです。
たとえば粉骨する時に、普通の骨壺だと思って穴が空いた骨壺を持ってまわれば、遺骨の粉を床にバラまいてしまいます。
このような骨壺をお墓に納骨せずに散骨や粉骨のために持って来られた場合には、必ず骨壺の底から零れ落ちた遺骨の破片や粉を、桐箱の中から集め直す必要があります。
水が溜まらないよりもっと大切な事

骨壺の中に水が溜まっては故人の遺骨が気の毒だと言う改善していくことはとても大切なことですが、もっと大切なこともあります。
土に還る事

骨壺の中に水が溜まることで骨が溶けくれるのなら、とても意義のある事で、骨の溶けた水を土に還せば自然葬になりますが、実際は骨は水に溶けません。
たとえ骨壺に水が入らなくて水没するようなことのない環境であっても、この状態で千年後も大して変わっていません。
お墓はそもそも土に還る場所なのですから、土に還るようにするのが本来の葬送なのです。