墓石の再利用

現代のお墓では墓じまいで回収した墓石を削り直して使うようなことはありませんが、昔は大切に使っていたことが分かります。
墓石のリサイクル

お墓の解体中に見つかるリサイクルのお話です、昔は物を大切に、そして最後の最後まで使うということが徹底していました。
これはお墓の花立ですが、取り外して裏を良く見てみると、文字が彫ってありますが、文政2年(1819)の墓石を削り直して作られたものです。もちろん通常の花立で使用する時には、これが墓石であることは全く分からないようになっていました。
文政2年(1819)と言えば今からちょうど2百年前の時代です。2百年前に亡くなった方ははたしてどんな方だったのでしょうか。車も高速道路も無い時代、近場で切り出した石を使って造られたお墓だったのでしょう。
この文字の面が裏になっていて、今までお墓に付けてあったので決して文字は見えなかったのですが、こうやって墓じまいの時に、ふとしたきっかけでこのお墓の歴史が明らかになることがあるのです。
昔からお墓の石は不要になっても他の用途に使うべからずと言われたものですが、こういう使われ方ならば良いのではないかと思います。
今の時代は何でも使い捨ての時代ですが、最後の最後まで使い切るという古の智慧を学びました。
文字を消さなかった理由
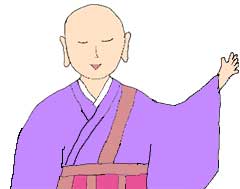
この石は土葬の時の竿石だったようで、年数が経過している割にははっきりと文字が読み取れますが、この方が誰であったのかは昔の人に聞いてみないと分かりません。
江戸時代で石を切り出すにしても全て人力で運ばれてきた事を思えば、使い古しの石材であっても貴重な資源だった訳であり、再利用しないと勿体ないという時代でしょうけれど、再利用するにしても普通でしたら文字を消して利用するのでしょうけれど、文字を消さなかった理由が何かありそうです。
私の想像ですけれど、朽ち果てて誰も管理されなくなり、打ち捨てられたような墓石を専門の石屋ではなくて、誰か子孫の者がタガネで削って作ったのではないでしょうか。
おそらく元々の身内一族の墓であり、朽ち果てていた墓石を供養のためにと削り直して使ったのではないかと想像するのです。
材料費が掛からなかった分、使わせて頂いた御先祖の名前はそのままにしておいたのではないかと思いますが如何なものでしょうか。


